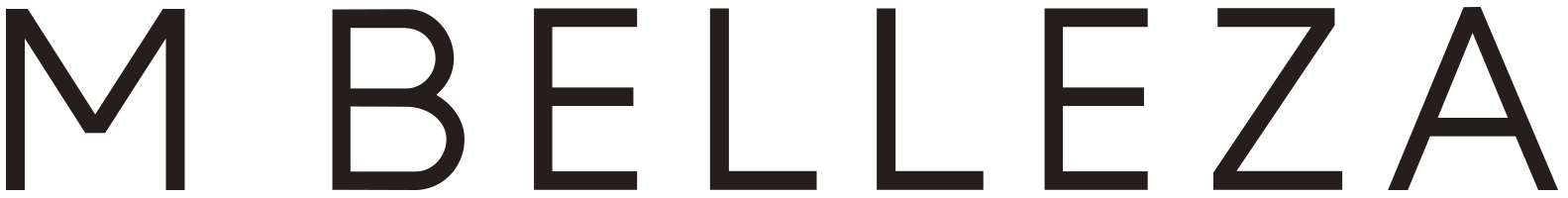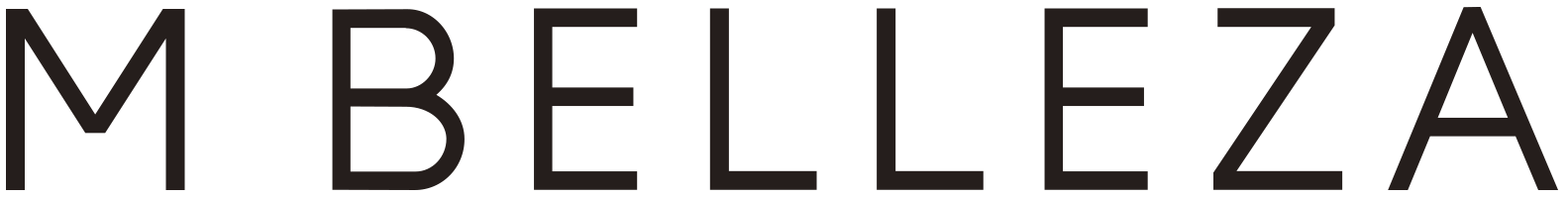エイジフリーで、
凛と美しく
お手入れ1日目。「なんかよさそう」から始まって、
使い続けることで美しさの可能性が広がっていく。
そして安心・安全を確信しながら
心をうるおし、肌を幸せに。髪をごきげんに。
そんな思いを込めてつくり上げたM BELLEZA。
2本目、3本目とリピート購入で
ケアを続けてくださるお客さまが増えてきました。
植物染めで日本の伝統色を継承する
京都「染司よしおか」の六代目、吉岡更紗さんもそのお一人です。
工房のこと、染織のこと、スキンケアへの思いなど
お話を伺いました。

「染司よしおか」六代目当主・染織家
吉岡更紗 Sarasa Yoshioka
1977年、京都府生まれ。大学卒業後、「イッセイミヤケ」の販売職を経て、「西予市野村シルク博物館」(愛媛県)で染織技術を学ぶ。2008年、五代目の吉岡幸雄氏のもと染織の仕事に就く。2019年、氏の急逝に伴い六代目に就任。




ようこそ、お越しくださいました。見ての通りの長屋。「えっ、ここ?」と思われたのでは(笑) かつては染め物屋が多かった綾小路にあったと聞いていますが、もうここで70年。四代目の祖父(吉岡常雄)が戦後、工房をこちらに移しました。良質な地下水に恵まれた土地という理由で。


イネ科の多年草、刈安(かりやす)でシルクのストールを染めているところ。日本古来の色が生み出されていく。
もともとこの辺りは巨椋池(おぐらいけ)という、湖と言ってもいいほどの大きな池があったところなんです。平安時代は舟を浮かべて蓮を見たり。伏見は名水の町、酒どころとして有名です。染色にも申し分のない環境です。鉄分の少ない水質が、それはそれは美しくきれいな色を引き出してくれます。「染司よしおか」では長屋の庭に井戸を掘り、地下100mから汲み上げた水を使っています。


染料になるのは紫根、紅花、蘇芳(すおう)、蓼藍、刈安(かりやす)、矢車などの植物。
地味な草木や実から、熟練の手業で鮮やかな色素がくみ出される。
染めの原点に戻り、植物染料を研究し、失われた日本の色の復活に余生を注いだ祖父。それを受け継ぎ化学染料を使うことを完全にやめ、研究を重ねたのが五代目を継いだ父(吉岡幸雄)でした。六代目となった私も「染司よしおか」の在り方を受け継いで、植物染めを通じて伝統色を復活させることを仕事としています。




二人の姉とは2歳ずつ違い。「更紗」という名前は、後を継ぐことを期待されていたかのようですが、インド更紗の研究をしていた祖父が本を出した時に生まれたから。あと、画数が良いということで。
自宅から近いこともあって、幼いころから工房にはよく来ていました。染めの現場には入れてもらえなかったけれど、子どもながら祖父の仕事をなんとなく理解し、染料の匂いも好きでしたね。
一方、父は出張が多く、おうちにいない人でした。幼いころは何をしているのかわかっていませんでした。「紫紅社」という出版社を経営し、美術工芸図書の編集を手掛け、染織史研究家や文筆家として評価されている人だったのですが。

英国のビクトリア&アルバート博物館に、日本の伝統色で染めた布や糸が永久保存されるなど、日本の色の第一人者だった吉岡幸雄さん。日本の伝統色466色を植物染めで再現した、吉岡幸雄氏の名著『日本色辞典』(紫紅社 2000年発行)。16刷のロングセラー。
そんな父が今でいう二刀流でやっていくと決めたのは、祖父が亡くなってから。出版社を続けながら、五代目としてやっていくことになりました。そもそも後を継ぐ気がなかった父。修行をしていない42歳。覚悟がいったと思います。
ただ、父は後継ぎの意思はなかったものの、京都の伝統や美術工芸への関心は強く、幼いころから寺社の行事によく連れて行かれました。わからないながらも、見聞きするあれこれは楽しく、私の歴史好きはそこから始まった気がします。


歴史好きが高じ、大学では東洋史を専攻しました。考古学も好きで、埋葬されたお墓から出てくる衣装や装飾品にもいたく感動する学生でした。記憶力も良かったので、そのまま研究者となって考古学を極めようかとも考えていたのですが、父が「そういうの研究している人って、つまらない人が多いんだよなぁ」。「豊かな話をする人が少なくてね」とある時に話していることを聞きまして(笑)。
父の言葉が全てではありませんが、逡巡し、私が選んだのは同じ生地の世界でも、憧れがあったファッションの道へ。結局イッセイミヤケに就職し、販売職につきました。お客さまとコミュニケーションをとりながら、素敵な一着に出会ってもらう。豊かな話のできる人間になるためにも、いい修行になりました。しかも仕事は楽しくて。その頃でしょうか、メイクがオンのスイッチになったのは。ただ、家業のことが頭のどこかに、心の片隅にあったのも事実です。「染司よしおか」には、社寺の伝統行事に携わるという大切な仕事があったからです。

「奈良・東大寺の修二会(お水取り)。初めて行ったのは3歳でした」と更紗さん。

たとえば725年から続く、東大寺二月堂の修二会(お水取り)。使われる椿の造花の和紙は、よしおかで染めています。ほかにも奈良薬師寺の花会式の造花に使う和紙の染め、京都石清水八幡宮の石清水祭に奉納する供花神饌、奈良時代の技法で作る幡(ばん)、伝統演劇の衣装などなど…。どれもこれも連綿と続く寺社の行事。うちの都合でやめることはできません。六代目として生きる覚悟を決めた一番の理由はそこでしたね。


結局イッセイミヤケには6年。退職してすぐ愛媛県の西与市野村町に移り住みました。「市立野村シルク博物館」で開かれていた染織講座に通うためです。養蚕農家さんの手伝いをし、繭から糸を作り、染め、機織りをして布に仕立てる。桑の葉が育つのは春から夏。思えば、紫外線もだいぶ浴びていましたが、本当に濃密な日々でした。
染織講座のカリキュラムは2年。みっちり学んで、2008年に京都に戻り父のもと一人の職人として染織の仕事につきました。最初は全然でしたけれど、講座で学んだ知識と販売で培ったコミュニケーション力で、職人さんたちとも徐々に信頼関係を築くことができていったように思います。「若いけれど、掘り下げて理解している」と。そんななか、父が急逝。2019年9月、心筋梗塞でした。


結局、父と一緒に仕事ができたのは11年足らず。まだまだ先と思っていた六代目にある日突然なってしまいました。祖父と父の片腕であった染師やスタッフに支えられて、使命感を感じながら、今に至ります。
職人さんたちと同じくらいの立ち位置に立つためにも、一生勉強です。あまたの植物から染料を見つけ出し、古の方々が愛した色を美しく染め上げていきたいと思います。
一方で、イベントのインスタレーションや、ロビーのディスプレイ、建築関係の仕事をいただく機会が増えてきました。そこには染色の可能性を感じています。



「見極める目」。これは父の教えでもあります。「目の記憶をしっかり整えるように」とよく言われました。染料になる植物も、できあがりを待つだけでなく、できるだけ栽培農家さんのところ行くようにしているのもそのためです。生育の様子を見せてもらったり、収穫に加わらせてもらったり。インドアのイメージがあるかもしれませんが、紅花摘みは、紫外線量がピークの6月、7月なんですよ。



「M BELLEZA」は姉から教えてもらいました。オールインワンをうたうだけあって、エビデンスに基づいた成分の充実ぶりがすごいというのが第一印象でした。全然煽らない地味な(失礼)、シックなホームページ。幹細胞順化培養液やエクソソームの調達先にもきちんと触れ、メイドインジャパンであることも私の心をくすぐりました。
実際、M
BELLEZAエクソステムバイタルフェイスリニューミストを使っていますが、最も感じるのは軽やかな使い心地とは相反する優れた保湿力とオールマイティな美容力です。特にキメの整い方が優秀で。キメが整えば毛穴も目立ちませんし、何よりベースメイクの仕上がりが格段によくなりました。私にとってメイクはオンのスイッチでもあるので、嬉しい限りです。お陰様で忙しく、オンの時間が長いので、逆に少ないオフの時間は存分に頼れるケアをしたい。その点においても、いい出会いになりました。洗顔の後の素肌に2プッシュ。3プッシュ。今では出張にも連れて行く間柄です。あれこれポーチに入れなくても、M
BELLEZAがあるから大丈夫。そんな感覚です。

染司よしおか 京都店
京都府京都市東山区西之町206-1
TEL075-525-2580
https://www.textiles-yoshioka.com/
場所は骨董店や茶道具の店などが並ぶ祇園の新門前通り。バッグやストールのほか、カードケースやポーチ、コースターなど、日々の暮らしに生きるアイテムが並びます。

更紗さんの著書『新装改訂版 染司よしおかに学ぶはじめての植物染め』『「源氏物語」五十四帖の色』(紫紅社)。